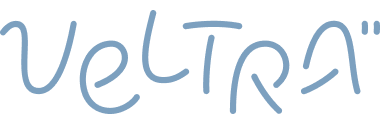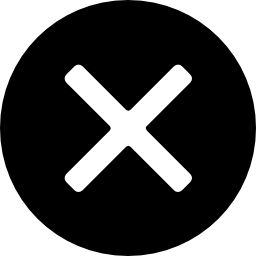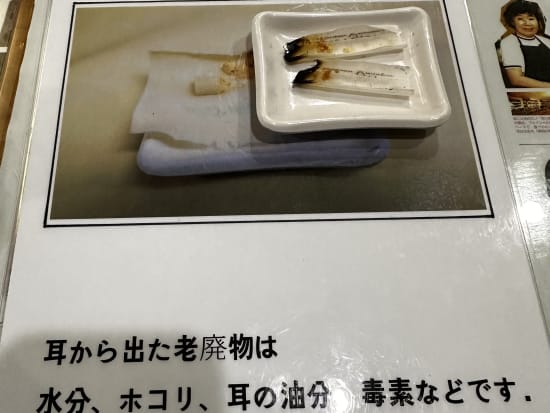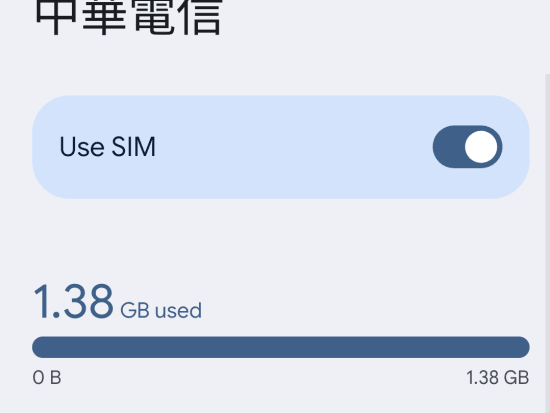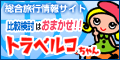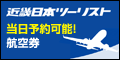体験談
560,739
アクティビティ
17,237
会員数
2,614,940
ベルトラおすすめの国内ツアー
今人気の海外ツアー
VELTRA STORE(ベルトラストア)
世界と日本の「美味しい」をお取り寄せ
おすすめ情報
エリアから探す
ベルトラ YOKKA
旅のTIPS・準備のために
ベルトラ コロリエ
会いにいきたくなる世界各地の素敵なツアーガイド
ベルトラおすすめガイド「コロリエ」のご紹介
最新5つ星体験談
ベルトラで取り扱いのエリア
日本国内
北海道
青森
秋田
岩手
宮城
山形
福島
新潟
富山
石川
福井
栃木
群馬
茨城
埼玉
千葉
東京
神奈川(横浜・箱根)
伊豆諸島・小笠原諸島
長野
岐阜
山梨
静岡
愛知
滋賀
三重
奈良
京都
大阪
兵庫
和歌山
愛媛
香川
高知
徳島
島根
鳥取
広島
岡山
山口
福岡
佐賀
宮崎
大分
熊本
長崎
鹿児島
屋久島
奄美大島・徳之島・沖永良部島・与論島
沖縄
種子島
五島列島・壱岐・対馬
ヨーロッパ
アイスランド
アイルランド
アルバニア
アンドラ
イギリス
イタリア
エストニア
オーストリア
オランダ
キプロス
ギリシャ
グリーンランド
クロアチア
コソボ
サンマリノ
ジブラルタル
ジョージア(グルジア)
スイス
スウェーデン
スペイン
スロバキア
スロベニア
セルビア
チェコ
デンマーク
ドイツ
トルコ
ノルウェー
バチカン市国
ハンガリー
フィンランド
フランス
ブルガリア
ベルギー
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ポルトガル
ポーランド
マケドニア
マルタ
モンテネグロ
リヒテンシュタイン
ルクセンブルク
ルーマニア
アフリカ
エジプト
エチオピア
ケニア
ザンビア
ジンバブエ
スーダン
セーシェル
タンザニア
チュニジア
ナミビア
パレスチナ
マダガスカル
南アフリカ
モーリシャス
モロッコ
ルワンダ
レユニオン
アジア
インド
インドネシア
ウズベキスタン
韓国
カンボジア
シンガポール
スリランカ
セブ島
タイ
台湾
中国
ネパール
バリ島
バングラデシュ
フィリピン
プーケット
ブータン
ベトナム
香港・マカオ
マレーシア
ミャンマー
モンゴル
ラオス
ランカウイ島